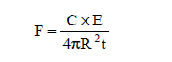
これは爆発性物質または物品の包装品、あるいは無包装の爆発性物品について、火炎に包まれた場合に、大量爆発または危険飛散物、放射熱および/または激しい燃焼、あるいはその他の危険な効果があるかどうかを判定するために行う試験である。
以下の物が必要である。
爆風圧測定装置、放射熱測定装置、および関連記録装置を使用してもよい。
16.6.1.3.1 輸送時の状態および形状の包装品または無法装品の必要数を、金属製格子の上にできるだけ相互に密着させて置く。包装品は飛散物が証拠スクリーンに当たる確率が最大になるような向きに置く。必要ならば、試験中保持するために包装品または無包装物品を鋼製帯で囲んでもよい。包装品または無包装品が火炎に包まれるように、燃料を格子の下に配置する。熱の散逸を防ぐために横風に対する対策が必要であろう。適切な加熱方法としては、800℃以上の火炎温度を作り出す木摺格子を使った火炎、液体またはガス燃料による火炎がある。
16.6.1.3.2 ひとつの方法としては、平衡を保った空気/燃料比をもち、事象を見えにくくする煙が出過ぎるのを防ぎ、様々な種類の包装爆発物を10~30分間反応させるのに十分な強さと継続時間をもって燃焼する木材火炎が挙げられる。適切な方法としては、空気乾燥した木材片(約 50 mm 平方)を、包装品または無包装物品を支える金属製格子(地上 1 m)の下に、その金属製格子の底面まで格子状に積み上げる方法がある。木材は、包装品または無包装品の面積よりも広く、各方向に 1 m 以上、格子間の間隔は約 100 mm となるように積み上げる。
16.6.1.3.3 木材火炎の代わりに、同程度の激しさの火炎が得られるならば、適切な液体燃料を満たした容器や、木材と液体燃料火炎の組合せを用いることができる。液体プール火炎を用いる場合、容器の面積は包装品あるいは無包装物品の面積よりも広く、各方向に 1 m 以上あることが必要である。格子台と容器の間隔は約 0.5 m とする。この方法を用いる前に、試験結果が疑問となるような、爆発物と液体燃料との間の消火作用または逆相互作用が起こりうるかどうかを検討しなければならない。
16.6.1.3.4 ガスを燃料として用いる場合、燃焼面積は包装品あるいは無包装物品の面積よりも広く、全ての方向に 1 m 以上あることが必要である。ガスは、火炎が包装品の周囲に均等に分散するように供給すること。ガス溜めは、火炎が少なくとも 30 分間継続するのに十分な大きさがなければならない。ガスの点火は遠隔で点火する火工品によるか、またはあらかじめ存在する点火源に隣接するガスの遠隔操作による放出による。
16.6.1.3.5 垂直な証拠スクリーンは、包装品あるいは無包装物品の端から 4 m の距離の3個の四分円の中にそれぞれ立てる。炎に長くさらされると、アルミニウムシートの飛散物に対する抵抗力が変化する可能性があるので、風下の四分円にはスクリーンを立てない。シートは、その中心が包装品または無包装物品の中心と同じ高さになるように設置するか、あるいは地上 1.0 m 未満の高さならば、地上に接するように設置する。試験前に証拠スクリーンに穴やへこみがある場合には、それらが試験中にできたものとはっきり区別できるように印をつける。
16.6.1.3.6 点火システムをセットし、燃料に2方向から(一方は風上)同時に点火する。風速が 6 m/s を超える場合には試験は行わない。試験機関が定める消火後の安全待機時間を遵守すること。
16.6.1.3.7 以下の事象を観察する。
16.6.1.3.8 試験は通常1回だけ実施する。ただし火炎のために使用した木材やその他の燃料が使い果たされたにも関わらず、未消費の爆発性物質が燃え残りの中や火の近くに多量に残った場合は、火炎の強さおよび/または継続時間を増すために、より多量の燃料を使って、あるいは別の方法を用いて、再度試験を行う。試験結果から危険等級が判定できない場合には、更に試験を行う。
16.6.1.4.1 結果を査定し製品を分類するための、図 10.3 (ボックス 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36)の質問に答えるために、以下の基準が用いられる。
16.6.1.4.2 大量爆発が起これば、その製品は危険等級1.1に分類される。大量爆発が起こったとみなされるのは、包装品または無包装物品の爆発性内容物すべての同時爆発を想定することによる実質的な危険が査定されるような、相当の割合で爆発が起こった場合である。
16.6.1.4.3 大量爆発が起こらなくとも以下のいずれかが起こった場合:
このような場合には、その製品は危険等級 1.2 に分類される。
16.6.1.4.4 製品が危険等級1.1 あるいは1.2 に分類されるような現象は起こらないが、以下のいずれかが起こった場合:
このような場合には、その製品は危険等級1.3 に分類される。
16.6.1.4.5 製品が危険等級1.1,1.2,1.3 に分類されるような現象は起こらないが、以下のいずれかが起こった場合:
このような場合には、その製品は危険等級1.4 で、S以外の隔離区分に分類される。
16.6.1.4.6 製品が危険等級1.1,1.2,1.3,1.4(隔離区分S以外)に分類されるような現象が全く起こらず、熱、爆風、飛散物効果がごく近くでの消火あるいはその他の緊急措置行動を著しく妨げない場合、その製品は危険等級1.4、隔離区分Sとされる。
16.6.1.4.7 危険な効果が全くない場合、その製品はクラス1から除外できるとみなされる。図 10.3 のボックス 35, 36 に示される可能性としては、
16.6.1.4.8 熱流束効果の評価におけるスケーリング時間測定に関する注
注:
表 16.2 質量変化に対する熱流束の比較値
| 1.3/1.4 | 1.4/1.4S | |||
| 質量(kg) | 熱流束(15 m) | 燃焼時間(s) | 熱流束(5 m) | 燃焼時間(s) |
| 20 | 1.36kW/m2 | 21.7 | 1.36kW/m2 | 195 |
| 50 | 2.5 | 29.6 | 2.5 | 260 |
| 100 | 4 | 35 | 4 | 330 |
| 200 | 6.3 | 46.3 | 6.3 | 419 |
| 500 | 11.7 | 63.3 | 11.7 | 569 |
注: 熱流束は(m/m0)2/3 を基準としてスケール化される。
時間は(m/m0)1/3 を基準としてスケール化される。
熱流束の値は次の方程式で計算する:
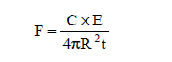
ここで:
| 物質 | 包装状態 | 現象 | 結果 |
| マスクキシレン | 3×50 kg ファイバーボードドラム | 穏やかな燃焼のみ | クラス1ではない |
図16.6.1.1 20 J および 8 J の運動エネルギーを持った金属飛散物の距離-質量関係(注)
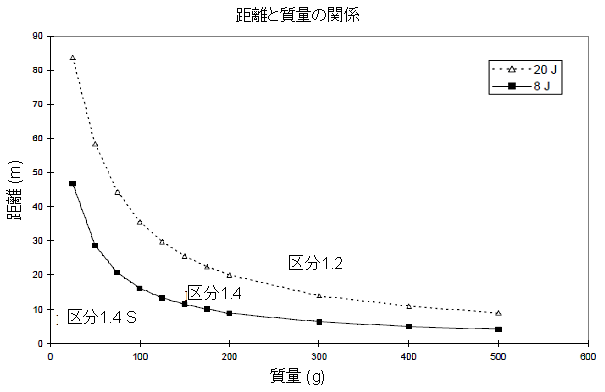
| 質量 | 飛散距離(m) | |
| (g) | 20 J | 8J |
| 25 | 83.6 | 46.8 |
| 50 | 58.4 | 28.7 |
| 75 | 44.4 | 20.6 |
| 100 | 35.6 | 16.2 |
| 125 | 29.8 | 13.3 |
| 150 | 25.6 | 11.4 |
| 175 | 22.43 | 10 |
| 200 | 20 | 8.8 |
| 300 | 13.9 | 6.3 |
| 400 | 10.9 | 4.9 |
| 500 | 8.9 | 4.1 |
20 J および 8 J の運動エネルギーを持った金属飛散物のデータ例
注: 図 16.6.1.1に示されたデータは金属飛散物に基づいている。非金属飛散物では違った結果が得られ、危険である可能性がある。非金属飛散物による危険も考慮する必要がある。