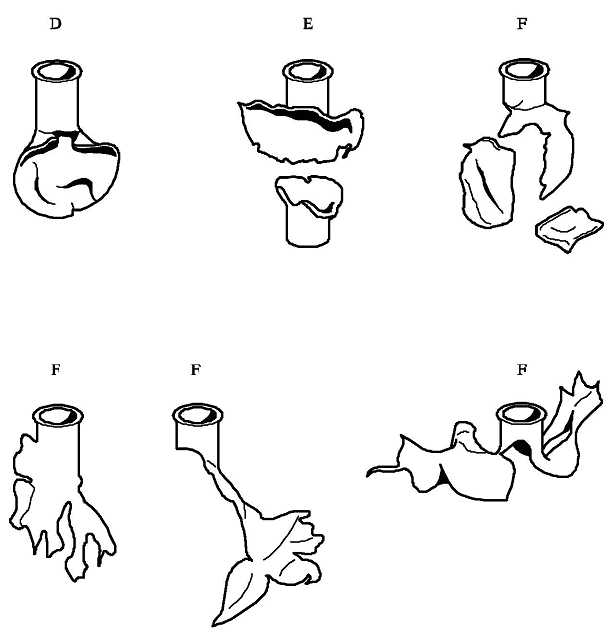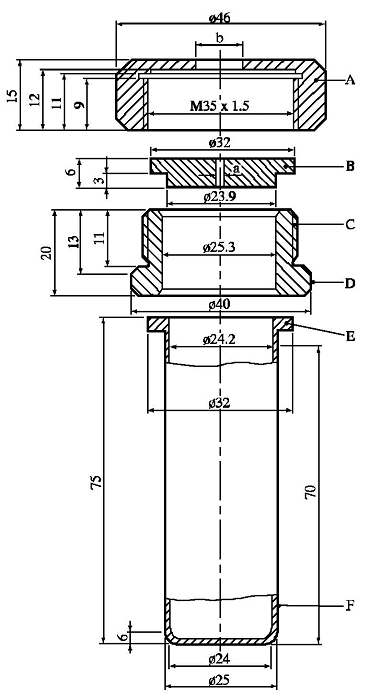
この試験は、高密閉状態において固体および液体試料を激しく加熱したときの感度を判定するために行う。
12.5.1.2.1 装置は、再使用可能な密閉装置を加熱および防護装置に取り付けた、使い捨て鋼管である。鋼管は、適切な質の深絞り鋼板であり、質量は25.5±1.0 g である。寸法を図 12.5.1.1 に示す。開放端にはフランジが付いている。試料の分解によって生じるガスが放出されるオリフィス付きの密閉板は耐熱性のクロム鋼製で、1.0、 1.5、2.0、 2.5、 3.0、 5.0、 8.0、 12.0、 20.0 mm 直径の穴のものを用意する。ねじ付きのつばおよびナット(閉鎖装置)の寸法を、図 12.5.1.1 に示す。
12.5.1.2.2 加熱はプロパンによって、圧力調整装置の付いた工業用シリンダーから、流量計を経由して行われ、連結管によって4つのバーナーに分けられる。特定の加熱速度が得られる場合は他の燃料ガスを使用してもよい。ガス圧は、較正手順で測定したとき、加熱速度3.3±0.3 K/s となるように調節する。較正は 27 cm³ のフタル酸ジブチルで満たされた鋼管(1.5 mm のオリフィス板付き)を加熱して行う。液体温度が135℃ から 285℃ に上昇するのにかかる時間(管の縁から 43 mm 下方中央に設置した直径 1 mm の熱電対で測定する)を記録し、加熱速度を算出する。
12.5.1.2.3 鋼管は試験中に破壊される可能性が高いので、加熱は防護溶接箱の中で行う。その構造と寸法を図 12.5.1.2 に示す。管は箱の向かい合った壁に開けた穴に通した2本の棒の間に吊す。バーナーの配置は図 12.5.1.2 の通りである。バーナーは口火または電気点火装置により、同時に点火する。試験装置は防護領域に置くこと。バーナーの炎がすきま風の影響を受けないようにする。試験の結果発生するガスや煙は残らず除去できるよう装備する。
12.5.1.3.1 通常、物質は受け取ったままの状態で試験するが、試験前に破砕する必要のある場合もある。固体の場合、各試験で使用される試料の量は2段階の予備手順を経て決定される。自重を計った鋼管を9 cm³ の試料で満たし、試料を 管の全横断面に対して 80 N の力を加えてタンピングする(注1)。もし圧縮可能ならば更に試料を加えて突き固め、管の先端から 55 mm の位置まで満たす。管を 55 mm の位置まで満たすのに使われる全質量を測定し、更に2回、80N の力で突き固めながら試料を追加する。最終的に先端から 15 mm の位置まで充填されるように、試料を加えるかまたは取り除く。
注1: 試料の摩擦感度が高い場合などは、安全のため、タンピングする必要はない。試料の物理的形態が圧縮によって変えられる場合、または試料の圧縮が運搬条件に無関係な場合(繊維状物質など)は、より典型的な充填方法を用いる。
2段階目の予備手順では、まず1段階目で得られた全質量の1/3 を鋼管にタンピングして詰める。更に2回の増量を 80 N の力でタンピングしながら行い、管の中の試料が先端から15 mm の位置になるよう試料の量を加減する。2段階目で決定された固体量を以降の各試験充填で用い、その1/3 ずつを3 回、各 9 cm³に圧縮する。(これは間隔リングの使用により容易にできる。)ゲルについては空隙の生成を妨げるよう特に注意して、液体とゲルを 60 mm の高さまで管に注入する。ねじ付きつばを下方から管にはめ込み、適当なオリフィス板を挿入し、二硫化モリブデン系潤滑油を塗った後、手でナットを締める。試料がフランジとプレートの間、あるいはねじの中などにはさまっていないよう注意する。
12.5.1.3.2 直径 1.0 mm から 8.0 mm のオリフィス板では、直径 10.0 mm のオリフィスのナットを、オリフィスの直径が8.0 mm 以上の場合は直径 20.0 mm のオリフィスのナットを使用する。鋼管は1回の試行にのみ使う。オリフィス板、ねじ付きつば、ナットは破損しなければ再使用できる。
12.5.1.3.3 鋼管は固定した万力の中に設置し、ナットはスパナで締め付ける。管を防護箱中の2本の棒の間に吊す。試験領域から立ち退き、ガスを供給してバーナーを点ける。反応までの時間と反応継続時間は、結果の考察に役立つ追加情報である。管が破裂しなければ、試験終了まで少なくとも5分間は加熱を続ける。各試験後、管の破片があれば集めて重さを量る。
12.5.1.3.4 試験結果は以下のように分類する。
注2: 密閉装置の中に残っている鋼管の上部は一つの破片としてカウントする。
“D”、“E、“F”の結果を図 12.5.1.3 に示す。“O”から“E”までの結果の場合は「不爆」、“F”,“G”、“H”の場合は「爆」とみなされる。
12.5.1.3.5 一連の試験は 20.0 mm のオリフィス板を用いた1回の試験から開始する。この試験で結果が「爆」になれば、オリフィス板とナットなしの管を使って試験を続ける(ただしオリフィス24.0 mm のねじ付きつば付き)。 20.0 mm で「不爆」の場合は、オリフィス径を 12.0 - 8.0 - 5.0 - 3.0 -2.0 - 1.5 - 1.0 mm と順次小さくして各1回の試験を「爆」となるまで続ける。続いて 12.5.1.2.1 に示したオリフィス径の順序に従って直径を大きくして、同じオリフィス径で「不爆」のみが3回観察されるまで試験を行う。試料の限界孔径は「爆」が得られた最大のオリフィス径である。直径1.0 mm で「爆」とならない場合、限界孔径は 1.0 mm 未満として記録する。
限界孔径が 2.0 mm 以上ならば、結果は「+」とみなされ、密閉下での加熱が試料に強い影響を及ぼすと考えられる。限界孔径が 2.0 mmより小さければ、結果は「-」とみなされ、密閉下での加熱が試料に強い影響を及ぼさないと考えられる。
| 物質 | 限界径 (mm) |
結果 |
| 硝酸アンモニウム(結晶) | 1.0 | - |
| 過塩素酸アンモニウム | 3.0 | + |
| ピクリン酸アンモニウム(結晶) | 2.5 | + |
| 1,3-ジニトロレゾルシン(結晶) | 2.5 | + |
| 硝酸グアニジン(結晶) | 1.5 | - |
| ピクリン酸(結晶) | 4.0 | + |
| PETN/wax (95/5) | 5.0 | + |
図 12.5.1.1 : 鋼管の組立部品
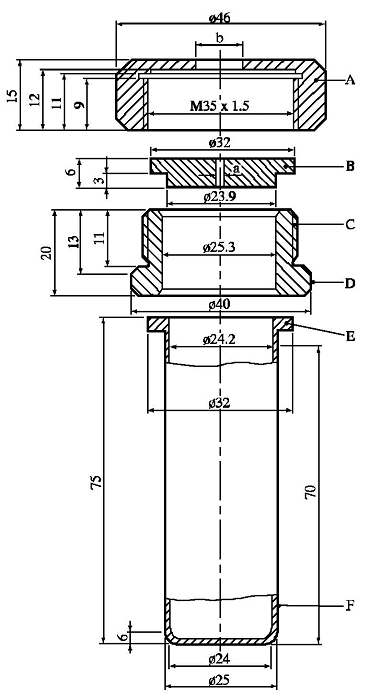
| (A) | 締め付け面(サイズ 41 スパナ用)付きナット (b = 10.0 または 20.0 mm) | (B) | オリフィス板 (a = 1.0 → 20.0 mm 直径) |
| (C) | ねじ付きカラー | (D) | 締め付け面(サイズ 36 スパナ用) |
| (E) | フランジ | (F) | 鋼管 |
図 12.5.1.2 : 加熱及び保護装置
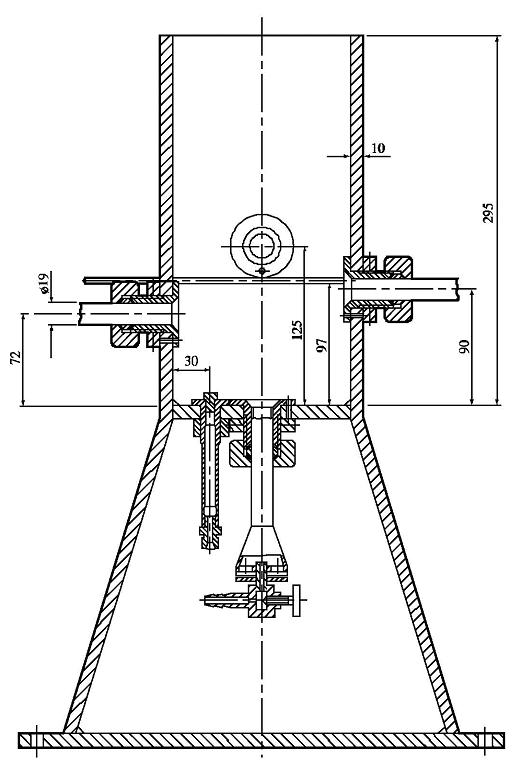
図 12.5.1.3 : D,E,及びFの結果の例